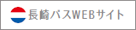TOP > 特集(2020年03月) > 【バス停ぶらりナビ27】★奥深さが魅力~深堀地区(前編)★
【バス停ぶらりナビ27】★奥深さが魅力~深堀地区(前編)★
2020年03月13日

カラフルに色付けされた恵比須さん。バス通りを見下ろすように高台に祀られています。長崎市南西部の深堀地区には、こうした恵比須さんが至る所に約80体祀られているのです。
今回の「ぶらナビ」は「深堀」バス停です。深堀地区は造船の町でもあり、市内で唯一城下町の佇まいを残す風情のある港町でもあります。ということで、今回は2回に分けてお伝えします。

なぜ、深堀地区に恵比須さんがたくさん祀られているのか?これは、深堀地区がかつて佐賀藩領だったことに由来しているようです。長崎市によると、関ヶ原の戦いの後、佐賀藩主が兵庫の西ノ宮本社から恵比須像を譲り受けたことから、佐賀藩内に恵比須が広まり、このため、佐賀藩領だった深堀地区に現在でも数多く残っているそうです。

では、なぜ恵比須さんに色を塗り始めたのでしょうか。深堀の恵比須さんは非常に崩れやすい砂岩でできているため、明治時代頃に恵比須さんを守るために祠を造りました。しかし、祠を造ることができなかったところでは、漁師たちが船を塗るペンキの余りで色を塗って、保護するようになったそうです。

深堀地区の恵比須さん、ユーモラスな表情でいつも静かに地区の人たちを見守っています。

さて、「深堀」バス停は三菱関連の会社や工場がずらりと建ち並んでいる一角にあります。「中央橋(高野屋前)」から乗車して約40分です。このバス停から海側に数分、歩いていくと小さな漁港に突き当たりました。

そこで、漁港に祀られている恵比須神社を撮影していたら、地元の方から「ここに去年から、めでたい海の生き物が住み着いているんだけど。」と教えていただきました。めでたい海の生き物!?海中に目を凝らしながら、ぐるりと歩いて探してみると・・。

「あっ、いました!!」海の底の方から、どこからともなく現れたのは立派なウミガメでした。

係留されている漁船の間をぬって、岸壁に近づいてきます。このウミガメは去年3月に初めて港に姿を見せたそうです。近くに住む人や漁師さんたちが、魚の切り身などをエサとしてあげていたところ、いったんは港外に出て姿を消しても、必ず戻って来るようになったそうです。

近くに住む元漁師の木村義夫さんは特に、ウミガメを可愛がっている一人です。ヒマが出来れば様子を見にやってきて、見かけたらエサをあげたりしています。
「このカメに名前はありますか?」「特別、名前は付けてないですよ。みなさん好きに呼んでいるようです。わたしはカメさんと呼んでます。1年になるので、姿が見えない時は寂しいですが、必ず戻ってきてくれてます。」

カメの姿を撮影しようと四苦八苦していたら、木村さんが「カメさん、カメさん」と声を掛けてくれました。そうしたら、カメがふわっと上がってきて、海面に顔を出してくれました。こんなこともあるんだなあと感心しました。
「カメは万年」と言われ、日本では長寿の象徴として縁起の良いものとされてきました。港町、深堀。恵比須さんを大事に祀ってきたこの地区だからこそ、ウミガメもやってきたのではないでしょうか。
「後編」は深堀地区の歴史を物語る建物や寺などをご紹介します。お楽しみに!
- 最新5件
- 【ホテル日航ハウステンボス】ホテル開業30周年「記念宿泊プラン」のご案内
- 長崎バス部品販売会2025 in 長崎バスグループ祭のお知らせ!!
- 坂のまちを走る あのバスが手元に
- 夏休みはバスで「ポケモン化石博物館」へ!
- エヌタス・長崎バス合同企画「えぬたん号バスツアー第6巻」レポート
- 月別一覧
- 2026年01月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年08月
- 2025年07月
- 2025年05月
- 2025年04月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年09月
- 2024年06月
- 2024年05月
- 2024年03月
- 2024年01月
- 2023年10月
- 2023年09月
- 2023年07月
- 2023年06月
- 2023年05月
- 2023年04月
- 2023年02月
- 2023年01月
- 2022年10月
- 2022年08月
- 2022年04月
- 2022年02月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年07月
- 2021年04月
- 2021年02月
- 2020年12月
- 2020年08月
- 2020年07月
- 2020年06月
- 2020年05月
- 2020年04月
- 2020年03月
- 2020年02月
- 2020年01月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年09月
- 2019年08月
- 2019年07月
- 2019年06月
- 2019年05月
- 2019年04月
- 2019年03月
- 2019年02月
- 2018年12月
- 2018年09月
- 2018年08月
- 2018年05月
- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月